建設業許可新規取得完全ガイド:5つの要件と申請手続き
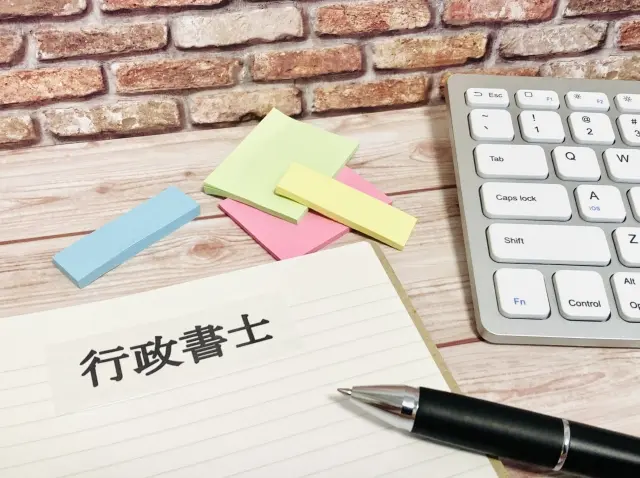
建設業を営む皆様にとって、建設業許可新規 取得は事業拡大と信頼獲得のために不可欠なステップです。
- 元請業者との契約
- 500万円以上の工事の請負
- 公共工事への入札参加
など、許可の有無が事業の可能性を大きく左右します。
しかし、建設業許可の取得は、
- 要件の複雑さ
- 申請書類の多さ
そして行政庁の厳格な審査から、「最初の大きな壁」と感じる経営者が多いのも事実です。
特に、初めて許可を取得する(新規取得)法人や個人事業主は、何から手を付ければいいのか、どの必要書類を集めればいいのかわからず、時間と労力を浪費しがちです。
今回の記事は、東京、埼玉、千葉、神奈川エリアを中心に建設業許可を専門とする行政書士が、新規取得を目指す皆様に向けて作成した完全ロードマップです。
建設業許可の基礎知識と区分
この章で伝えたい結論:建設業許可は、請負金額や発注者の違いにより一般建設業と特定建設業、知事許可と大臣許可の四つの区分に分かれます。
新規取得時に自社がどの区分に該当するかを正確に把握する必要があります。
許可の種類と判断基準
建設業許可には、大きく分けて二つの種類と二つの区分があります。
新規取得時、この判断を誤ると、その後の申請手続きや必要書類が大きく変わります。
-
一般建設業許可:税込み500万円以上の工事を請け負う者、且つ元請工事の場合に下請への発注額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合に該当します。大半の中小建設業者はまずこれを目指します。
-
特定建設業許可:元請工事であり、かつ、下請への発注額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合に該当します。一般に比べ財産的基礎の要件が格段に厳しくなります。
知事許可と大臣許可
-
都道府県知事許可:一つの都道府県内にのみ営業所を設置して事業を営む場合の許可です。
-
国土交通大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設置して事業を営む場合の許可です。
29業種の選択と専門性
建設業許可は29の業種に分かれています。
新規取得時には、自社が実際に行ってきた建設工事の実績に基づき、必要な業種を選択します。
例:土木一式工事、建築一式工事、管工事、電気工事、内装仕上工事など。
建設業許可 5つの要件の詳細
この章で伝えたい結論:建設業許可を新規取得するためには、建設業法で定められた「経営の要件」「専技の要件」「財産の要件」「誠実性の要件」「欠格要件に該当しないこと」の5つをすべて満たす必要があります。
要件1:経営業務の管理責任者(経管)の設置
法人の常勤役員などの中に、建設業の経営を適切に管理できる者がいることが求められます。原則的な要件は以下の通りです。
-
役員(取締役など)としての経営経験が5年以上ある者。
-
役員に準ずる地位(執行役員、本部長など)として経営業務を直接補佐した経験が6年以上ある者。
経営業務管理責任者制度の廃止はいつ?要件変更と今後の対策を徹底解説
要件2:専任の技術者(専技)の設置
営業所ごとに、請負契約の適正な締結や履行を確保するための専門的な技術を有する者が必要です。
専技になるための主な経験や資格は以下の通りです。
-
指定された国家資格などの保有者(例:1級施工管理技士、建築士など)。
-
指定の学科を卒業後、一定期間(高校卒で5年、大学卒で3年など)の実務経験を有する者。
-
許可を受けたい業種に関して10年以上の実務経験を有する者。
要件3:財産的基礎(金銭的信用)の確保
工事を施行するための必要な資金力や信用があることを証明する必要があります。
-
一般建設業:直前の決算期において、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力(預金残高証明など)があること。
-
特定建設業:厳格な財務要件(例:欠損の額が資本金の20%以下、流動比率が75%以上など)が課せられます。
建設業許可の財産的要件とは?自己資本500万円の基準と証明方法を解説
要件4:誠実性の確保
法人及びその役員、または個人事業主本人が、請負契約の履行に関し、不正な行為や不誠実な行為を行うおそれがないことが求められます。
具体的には、過去に建設業法や関連法令に基づく処分(営業停止など)を受けていないかを確認します。
要件5:欠格要件に該当しないこと
法人またはその役員、専任技術者などが、建設業法で定められた欠格事由(禁錮以上の刑の執行終了から5年を経過していない、破産手続き開始決定を受けて復権を得ていないなど)に該当しないことが必須です。
建設業許可が取れない時の不許可理由と対処法:行政書士が教える最終解決戦略
建設業許可 申請手続きの流れ
この章で伝えたい結論:建設業許可の申請手続きは、資料収集と行政庁への事前相談が最も重要です。
許可が下りるまでは通常2~4ヶ月の時間を要するため、計画的な準備が解決の鍵となります。
ステップ1:要件の確認と事前相談
まず、自社が経管、専技、財産の5つの要件を満たしているかを厳密にチェックします。
特に、経管と専技の実務経験証明に使用する資料を持ち込み、行政庁の窓口で事前に相談することが重要です。
(東京都などは事前相談を推奨しています)。
ステップ2:必要書類の収集と作成
許可申請には、法人の登記簿謄本や決算書、税の納税証明書などの公的書類に加え、
- 経管や専技の経験を証明する証明書
- 契約書
- 請負実績を示す資料
など、膨大な数の必要書類の作成と収集が必要です。
-
建設業許可 必要書類の例(一般)
-
許可申請書一式(様式第1号)
-
経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
-
専任技術者証明書(様式第8号)
-
誓約書(様式第10号)
-
財産的基礎を証明する書類(残高証明書など)
-
ステップ3:申請書類の提出と審査
作成した申請書類を、メインの営業所を管轄する都道府県の建設業担当課などに提出します。
提出時に許可手数料(知事許可で9万円、大臣許可で15万円)を納付します。
その後、行政庁による厳格な書類審査が行われます。
不備がある場合は追加の資料提出や補正を求められます。
ステップ4:許可の通知と登録
審査を通過すると、行政庁から許可決定の通知があり、許可番号が付与されます。許可が下りた後は、速やかに営業所などの定められた場所に「建設業の許可票」を掲示する義務が生じます。
建設業許可証明書と通知書の違い:用途、取得方法、有効期限を完全解説
建設業許可 費用の内訳と相場
この章で伝えたい結論:建設業許可の新規取得にかかる費用は、主に「行政庁への手数料」「必要書類の交付費用」「行政書士への報酬(依頼する場合)」の3つに分かれます。
総額であれば知事許可の場合30万円~50万円程度が相場となります。
行政庁への法定手数料
これは許可を申請する際に行政庁に納める必須の費用です。
-
都道府県知事許可(新規):90,000円(許可の種類にかかわらず)
-
国土交通大臣許可(新規):150,000円
必要書類の交付費用
申請に必要な公的資料を取得する際にかかる実費です。
-
登記簿謄本(登記事項証明書):1通あたり600円程度(法務局)
-
納税証明書:数百円(税務署)
-
身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行):数百円
- 登記されていないことの証明書(法務局本局で発行):数百円
建設業許可 行政書士への報酬
自力での申請が難しい場合、行政書士に「建設業許可 申請代行」を依頼します。
報酬は業務内容や地域により異なりますが、一般建設業の知事許可(新規)であれば、25万円~40万円程度が相場となります。
建設業許可 行政書士の活用と選び方
この章で伝えたい結論:建設業許可の新規取得は、必要書類の選別や要件の証明に高い専門性が求められるため、建設業許可 行政書士の活用は「時間の節約」と「確実な許可取得」に繋がる最も現実的な解決策です。
行政書士に依頼する3大メリット
-
時間の節約:膨大な必要書類の作成と収集、行政庁への繰り返しの相談を代行し、経営者の時間を本来の業務に集中させます。
-
不許可リスクの回避:要件の判断や証明資料の適否を専門家の立場で事前にチェックするため、不許可になるリスクを最小限に抑えられます。
-
鮮度の高い情報と対応:建設業法は改正が多く、地方ごとに審査基準に微妙な差が生じます。弊事務所のように関東エリアに特化した専門行政書士は、最新の情報と権威を持ち対応します。
良い行政書士を選ぶための比較ポイント
-
実績と専門性:建設業許可専門を謳っているか、実績数を公開しているかを確認します。弊事務所のように、新規取得の難しい東京都を含む関東エリア(埼玉、千葉、神奈川)での実績が豊富な事務所を選ぶのが安心です。
-
初回相談の有無と明瞭な費用:新規取得の難しい要件判断に関して、丁寧にヒアリングを行い、報酬や実費の内訳を明瞭に提示してくれるかを比較します。
知事許可と大臣許可の比較
この章で伝えたい結論:新規取得時は自社の営業所の場所で申請先が変わります。大臣許可の場合は、管轄が地方整備局となるなど、申請先や必要書類の提出方法が大きく異なります。
-
知事許可の場合:申請書類は営業所のある都道府県庁舎へ提出します。
-
大臣許可の場合:主たる営業所を管轄する地方整備局(国土交通省)へ提出します。
建設業許可必要書類の代替と証明
この章で伝えたい結論:経管の役員経験や専技の実務経験を証明する際、公的書類が不足している場合は、契約書、請求書、職制規程、組織図などの代替資料の収集と説明が重要になります。
-
実務経験証明の難しさ:「10年以上の実務経験」で専技要件を満たす場合、過去の勤務先が廃業していると、「実務経験証明書」の発行を受けられない可能性があります。この場合、自己の資料(給与明細、発注書など)を総動員して証明する必要があります。
財産的基礎の解決策(融資と増資)
この章で伝えたい結論:一般建設業許可の財産要件である500万円が不足する場合、銀行融資や増資により資金調達能力を示します。残高証明書は申請日に近い日付のものが必要です。
-
融資の活用:日本政策金融公庫などからの融資で資金を確保し、それを含めた500万円以上の残高証明を提出します。融資が決定している場合も、申請時点で実際に通帳に入金されていることが必須です。
個人事業主の法人成りと許可承継
この章で伝えたい結論:個人事業主として許可を取得した後、法人成りする場合は、許可の「承継」は認められず、法人として新たに建設業許可を新規取得する必要があります。
-
法人成りの特例:法人化後の新規申請時は、個人事業主時代の経営経験や技術経験を法人の要件にそのまま活用することができます。これは、個人事業主と法人の経営者が同一人物である場合に限られます。
許可取得後の義務(更新と変更届)
-
変更届の忘れに注意:変更届の提出を怠ると、5年後の更新申請が受理されないなど、大きな問題に発展する可能性があります。変更届の提出期限は事項ごとに異なるため、常に記録を残しておく必要があります。
建設業許可を取らないといけない場合(法令解説)
建設業許可を有するメリットとデメリットの比較
メリット:500万円以上の大きな工事が請け負える、公共工事の入札に参加できる、社会的信用が向上するなど。
デメリット:許可取得と維持に費用と手間がかかる、常に経管・専技の常勤配置義務が生じる、定期的な変更届の提出義務が生じるなど。
東京、埼玉、千葉、神奈川エリアの特色
関東エリアの各都道府県は人口密度や建設需要が高いため、建設業者の数が多く、許可審査が厳格な傾向にあります。
特に東京都は審査が複雑であると言われているため、地元の行政書士に依頼することが不可欠です。
特定建設業許可の厳格な財務要件
特定建設業を新規取得する際は、一般建設業とは比べ物にならないほど厳格な財務要件(法第15条第3号)が課せられます。
財務諸表の分析に加え、会計士や税理士との連携も必要となります。
CCUSと建設業許可の関連性
CCUS(建設キャリアアップシステム)は、許可要件ではありませんが、適正な労務管理を行っている証拠として、経営事項審査(経審)で評点が加算されます。
新規取得の段階から導入を検討することが、将来的な事業拡大に繋がります。
佐藤栄作行政書士事務所 |
公開日:2025.11.17 07:30
更新日:2025.11.18 20:08



